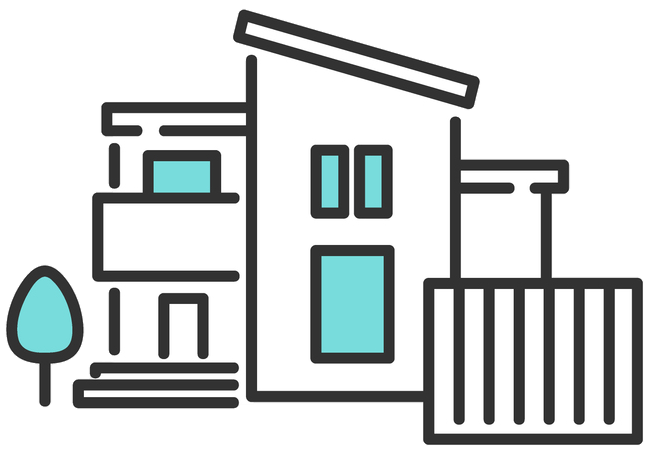不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
相続した自宅の評価額の計算方法とは?建物・土地の評価額と相続税の計算方法を紹介
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
親族から不動産を相続したら、相続税を納付しなければなりません。
その相続税を算出するためには、相続した不動産の評価額がいくらであるかを知っておく必要があります。
不動産の評価額を把握しておけば、今後売却する時の助けになるだけじゃなく、納付すべき相続税の税額の形状を行うのにも役立ちます。
今回は、相続した住宅の評価額の求め方と、相続税の計算方法について詳しく解説します。
相続した不動産を売るには?売却の流れや相続税・売却時にかかる税金の注意点
相続した自宅の評価額を求める際の考え方
亡くなった親族から住宅や土地などの不動産などの財産を相続したら、相続税を納めなければなりません。
実際に相続税を納めることになれば、相続した財産の評価額によって、税率が変動します。
例えば、今回のように住宅を故人から相続した場合、住宅の評価額を基にした相続税を納税しなければならず、相続人もまた住宅の評価額がいくらであるかを把握している方は限りなく少ないです。
住宅の評価額を求めるときは、建物と土地の2つに分けて評価額を求めます。
分譲住宅を購入するとき、建物と土地が一体となった資産として考えるのが自然ですが、登記及び税務上は、建物と土地の2つの資産を取得したことになります。
したがって、相続した受託の評価額を求めるときは、建物と土地、それぞれの評価額を求めたうえで相続税を算出していきます。
相続した自宅の評価額の求め方
相続税を求める前に、相続した不動産の評価額を知ることから始めなければなりません。
前述したように、戸建て住宅を相続したときは、建物部分と土地部分の評価額をそれぞれ求めたうえで、相続税を計上します。
ここでは、建物と土地の評価額の求め方を紹介します。
家屋(建物部分)の評価額
建物部分の評価額は、毎年6月に送付される固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額が、評価額になります。
手元に固定資産税の納税通知書が見当たらない場合は、市役所で固定資産税評価証明書を取り寄せることで確認ができます。
土地の評価額
土地の評価額を求めるときは、路線価を使用して評価額を算出します。
路線価とは、その年の1月1日時点における主要道路に面した1㎡あたりの土地価格を公示したもので、毎年7~8月の間に国税庁が公表しています。
路線価は主に、相続税と、贈与税を計上する時に使用します。
なお、土地の評価額を求めるときは、この路線価を使用して算出するわけですが、相続した不動産によって使用する計算方法が異なります。
例えば、相続した家が市街地にある場合は、路線価方式を使用し、路線価が設定されていない場合は、倍率方式を使用して求めます。
路線価方式
路線価方式では、路線価を用いて計算し、路線価は、国税庁のホームページ上で確認できます。
なお、路線価方式で評価額を求める際は、以下の計算式を用いて算出します。
土地の評価額 = 1㎡あたりの路線価 × 敷地面積
計算する土地の形が整形地(整った四角形)じゃない不整形地(台形など)の場合は、路線価に補正率をかけて加算・減算を行います。
補正率も路線価同様、国税庁のホームページ上に掲載されていますが、自分で計算するよりも、相続専門の税理士等に依頼して評価額を算出するのがおすすめです。
倍率方式
路線価が定められていない地域にある住宅を相続した場合は、倍率方式を利用して評価額を算出します。
土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
倍率方式で使用する評価倍率は、地域によって異なり、この倍率も国税庁のホームページ上に掲載されています。
なお、倍率方式では整形地・不整形地問わず、固定資産税評価額に評価倍率をかけるだけで算出できます。
相続税評価額の調べ方は?計算方法や減額できるケースを解説【モデルケース】評価額によって発生する相続税の計算方法
ここからは、下記のモデルケースを使用して相続税を算出していきます。
- 法定相続人:配偶者、子供2人
- 基礎控除額:3,000万円+(3人×600万円=4,800万円
- 相続評価額:5,500万円
- その他の財産4,000万円
- 被相続人の配偶者が自宅を相続
- 被相続人の子供にその他の財産の2,000万円ずつが相続される
財産から基礎控除を引く
手始めに相続する財産、自宅とその他の財産の評価額を合算し、そこから基礎控除を差し引きます。
5,500万円(自宅)+4,000万円(その他)-4,800万円(基礎控除)=4,700万円
相続税の総額を求める
次に、前述で算出した金額に、法定相続分をかけて、相続税の総額を算出します。
今回のモデルケースの場合は、配偶者に1/2、子どもに残りの等分をかけて計算します。
なお、相続税の税率は所得金額によって変動します。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記表を用いて、それぞれの所得額と相続税を計上すると以下の計算式になります。
- 4,700万円×1/2=2,350万円
- 2,350万円×15%(相続税)=352.5万円
- 352.5万円-50万円(控除額)=302.5万円
- 4,700万円×1/2×1/2=1,175万円
- 1,175万円×15%(相続税)=176.25万円
- 176.25万円-50万円(控除額)=126.25万円
最後に、上記で算出された金額を合算して相続税の総額を算出します。
302.5万円+126.25万円+126.25万円=555万円
実際の取得割合で相続税の総額を按分計算
実際の取得割合で相続税の総額を算出すると、以下のようになります。
5,500万円(自宅)÷9,500万円(遺産総額)×555万円(相続税)=約316.35万円
2,000万円(その他)÷9,500万円(遺産総額)×555万円(相続税)=約116.55万円(1人当たり)
適用できる税額控除を差し引く
最後に、適用される税額控除を利用していきます。
今回のモデルケースの例の場合は、配偶者に配偶者控除が適用されます。
配偶者控除は配偶者が相続した遺産が1.6億円以下、もしくは遺産が法定相続(1/2)以下であれば相続税が発生しません。
今回の場合は、配偶者が相続した遺産総額が1.6万円以下になるため、控除によって、相続税が発生しません。
しかし、その他の遺産を相続している子ども2人には、相続税の納付が必要になります。
相続税の税負担軽減ができる「小規模宅地等の特例」
ここまで、建物・土地の評価額の求め方と相続税の計算方法を紹介してきました。
相続税の納税額は、相続した資産価値や量に応じて高額になっていきます。
そのため、相続人の中には、税負担の軽減を図りたいと考えている方がいます。
税負担軽減の1施策として利用できる方法として、小規模宅地等の特例というものがあります。
- 減額面積:330㎡まで
- 減額割合:80%
ここでは、小規模宅地等の特例の適用条件とモデルケースによる減額の割合を紹介します。
適用条件
小規模宅地等の特例が利用できるのは、以下の条件を満たしている方が相続した時に適用されます。
- 配偶者
- 同居している親族
- 別居中で一定条件を満たした親族(配偶者・同居人がいない場合のみ)
適用条件3つの目の「別居中で一定条件を満たした親族」における一定の条件とは、住宅の相続開始時期の3年以内に住宅を所有していない子どもが、相続わきに、対象の家を所有するものとなり、住み続けた時に小規模宅地等の特例が適用されます。
なお、マンションのように、所有権が別になっているものや、故人が所有していた敷地内で別々の住居で生活を送っている場合は、「生計を共にしていたか」が適用条件になります。
【モデルケース】減額される割合
ここからは、小規模宅地等の特例が適用された場合の相続税の計算を行います。
モデルケースとして、以下の数値で計算を行います。
- 建物の評価額:2,000万円
- 土地(330㎡以下)の評価額:3,000万円
- 相続人:1人
上記条件下で基礎控除と相続税を計算していきます。
| 算出項目 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円+(600万円×1人) | 3,600万円 |
| 課税遺産額 | 5,000万円-3,600万円 | 1,400万円 |
| 相続税 | 1,400万円 × 15% - 50万円 | 160万円 |
実際には、160万円の相続税を納めなければなりませんが、小規模宅地等の特例が適用された場合、土地評価額の80%が減額になるため、600万円になります。
そこに、建物の評価額2,000万円を加えると、2,600万円になり、基礎控除額の3,600の範囲に留まるため、相続税の納付が免除されます。
相続した自宅の価値を求める際はその道のプロに相談するのが最適
ここまで、相続した住宅の評価額の求め方と、相続税の計算方法について詳しく解説してきました。
故人から不動産を相続すれば、相続税の納付を行わなければならず、納付額を出すには、建物と土地の評価額を知っておくことが大切です。
建物の評価額は、固定資産税の納付通知書から把握できますが、土地評価額の調査は建物の評価額を調べるよりもやや複雑です。
個人で調べることもできますが、正確な納付額を算出するなら、相続専門の税理士に依頼して算出してもらうのが最適です。
また税負担軽減の施策として、小規模宅地等の特例や、生前に贈与してしまうなど、様々な施策があります。
困ったときは、一人で解決するのではなく、まずはその道のプロに相談して解決するようにしましょう。

関連する他の記事
親族から不動産を相続したら、相続税を納付しなければなりません。
その相続税を算出するため…
故人から不動産を相続すれば、売却を選択される方が大勢います。
当記事では、相続した不動産…

 当サイトは東晶貿易株式会社が
当サイトは東晶貿易株式会社が