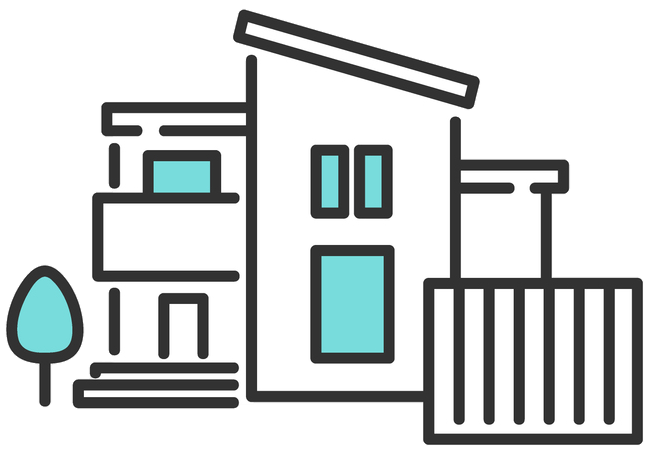不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
老後の住み替えに潜む恐ろしい罠とは?よくある失敗事例とリスク回避のポイント
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
仕事をリタイアしたら、理想の暮らしを求めて住み替えを選択する方も多いです。
また、中には対の棲家として、今住んでいる家を離れて賃貸に住むのか、コンパクトサイズのマンションを購入するかなど、選択に迷っている方も多いことでしょう。
今回は、老後の住み替えで失敗してしまいがちな罠や、リスクを回避するための対処法を解説していきます。
→スーモカウンターの口コミ・評判と気になるデメリットを徹底解説
老後の住み替えに潜む恐ろしい罠とは?
平均寿命が伸びたことによる資金不足リスク
令和3年の厚生年金の平均受給額は14万6千円で、老後の生活には小さな出費も大きな打撃となる可能性があります。
平成20年10月23日時点の内閣府の調査では、65歳以上の人口が全体の28.9%に達し、平均寿命も男性81.47年、女性87.57年と伸びており、老後の長期生活資金が必要となります。
その結果、貯蓄が不足し、資金がショートするリスクがあります。
このリスクは、年金制度の改革や経済状況の変化によって更に増大する可能性があります。
賃貸に住む人が増えたことで生じるリスク
高齢者が賃貸住宅を契約することは難しいです。
また、賃貸では修繕費等はオーナー負担で、住居費は家賃と管理費のみですが、老後に住み替えをする際、地域住民に馴染むことが難しい場合もあり、自己実現や自己超越欲求を満たすことが難しいというリスクもあります。
さらに、賃貸契約の更新や物件の維持管理に関わる問題も存在します。
年金以外の収入源を確保するのが難しくなる
老後には、現役時代と比べて収入が大幅に減少します。
その結果、住宅ローンの返済能力が低下し、ローン審査が通りにくくなる可能性があります。
さらに、退職金を住み替えのために全て使ってしまうと、その後の生活費が厳しくなるリスクもあります。
また、投資や副業などによる収入源の確保が難しくなる可能性もあります。
持ち家の売買が難しくなる
老後の住み替えに伴う持ち家の売買は、現在よりも高い価格で物件を購入する必要があるため、財政的な負担が大きいです。
さらに、持ち家を購入した場合、その家が将来的に子供たちにとっての重荷になる可能性もあります。
また、不動産市場の変動や物件の価値評価にも注意が必要です。
老後の介護リスク
平成20年10月23日時点で、日本の高齢者の9割以上が在宅で暮らしており、要介護の高齢者のうち約8割も在宅で生活しています。
ただし、介助の必要性が高まると、自宅での介護を希望する人が減少し、介護施設への移住を希望する傾向が見られます。
これに伴い、医療費や介護費用が増加し、収入が減少するとそれらを負担することが難しくなります。
また、高齢者が多くなると、介護サービスの需要が増え、供給が追いつかない可能性もあります。
これに加えて、自宅での介護が難しくなった場合の介護施設への移住の問題も存在します。
介護者世帯へもたらすリスク
介護が必要になると、家族が介護者となるケースがあります。
しかし、介護負担が増えると介護者自身の生活や健康に影響を及ぼすことがあります。
また、住宅のバリアフリー化が必要になるなど、住まいに関連する負担が増大することも予見されます。
この他にも、介護者の就労制限やメンタルヘルスの問題も考えられます。
老後の住み替えのメリット
住みやすさと便利さの向上
老後の住み替えは、生活スタイルに合った居住環境を提供する大きなメリットがあります。
たとえば、加齢により運転が困難になった場合、食料品の買い出しや日常生活が困難になる可能性がある郊外から、徒歩圏内にスーパーや病院がある地域への住み替えを考えることができます。
加えて、自身のライフステージに合わせて環境を変更することで、「老後は田舎でゆっくり暮らしたい」や「南の島へ移住したい」といった願望も実現可能となります。
また、戸建てを選択すると、ガーデニングや家庭菜園といった趣味を楽しむ空間が生まれる一方、大きな声のボリュームなど、周囲への配慮も求められます。
老後資金と生活費の節約
また、老後の住み替えは節約の一環ともなり得ます。
例えば、リフォーム工事で住宅内をバリアフリーにするのは大変ですが、住み替えをすることでこれを避けられます。
さらに、相続税の納税額は遺産の価値を現金換算したものに税率をかけて計算します。
そのため、現金を不動産に替えることで節税効果があると言えます。
ただし、相続した不動産の売却は様々な要因で簡単にはいかない可能性もあります。
その他、高齢者向けの住宅情報を提供する組織から、自分の足下を見て老後の住まいを考えるようアドバイスがあります。
シニア向け分譲マンションなどの選択肢も存在し、これらは自由な生活が可能な一方、売却や賃貸に出す際には特殊な条件があることを理解しておく必要があります。
老後の住み替えの選択肢
高齢者になると生活の自由度、安全性、利便性など様々な面で住み替えを考える方が増えてきます。
以下では、老後の住み替え先として選ばれることが多い、戸建て、マンション、シニア向け住宅、公営施設について詳しく解説します。
戸建て
戸建ての魅力は自由度の高さにあります。
例えば、音楽を演奏したり、ペットを飼ったり、庭でDIYを楽しむなどが可能で、自身の生活スタイルに合わせて調整できます。
しかし、高齢者が住む場合には注意点もあります。
段差が多いことや、2階への階段の上り下りが大変な点、さらには住人が特定されやすく、犯罪のリスクも無視できません。
しかし、所有すれば自分の資産になるため、適切な管理のもとで安心して暮らせます。
マンション
一方、マンションは戸建てと比べてバリアフリーが整っており、エレベーターによって高層階への移動も容易です。
災害時にエレベーターが使用できないことが懸念点ですが、そのような事態は稀です。
騒音には気をつける必要がありますが、安全性や管理の手間が少ない点で高齢者にとっては魅力的です。
また、老後の住み替え先として多く選ばれています。
シニア向け住宅
シニア向け住宅は、シニア世代が住みやすいように設計されており、必要に応じて生活サポートや介護サービスを受けられます。
シニア向け分譲マンションは、自由度が高く、また購入後は自分の資産となります。
一方、サービス付き高齢者向け住宅は、自立した高齢者から要支援者まで幅広く受け入れており、安否確認や生活支援サービスを受けられるため、安心して生活できます。
ただし、介護サービスは必ずしも付いていないため、個別に契約する必要がある場合があります。
公営施設
公営施設に含まれる有料老人ホームは、食事や洗濯、掃除などの生活支援や、介護、健康管理などのサービスを提供しています。
24時間介護スタッフが常駐し、介護サービス費が定額なため、経済的な安定性もあります。
有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」の3種類に分けられ、それぞれの状況に応じて選べます。
公営施設はシニア向け住宅よりも入居難易度が低く、より多くの選択肢があります。
老後の住み替えを成功させるためのタイミングの考え方
住み替え計画は50代から考える
老後の生活について考えるとき、一番重要な要素の一つが「住まい」です。
私たちの住まいはライフスタイルや健康状態により変わる可能性があります。
子供たちが家を出て独立すると、その家が大きすぎて維持が困難になることもあります。
また、年齢とともに身体の状態も変わり、階段の多い家や不便な場所に住むことが困難になるかもしれません。
そこで、老後の住み替え計画は早めに考え始めることが肝心です。
その準備としては、まず子どもたちが独立したタイミングで家の利用・活用方法を考えることが重要です。
この段階で「利活用」が可能かどうかを見極めることが大切で、例えば不要な部屋を貸し出す、家の一部を店舗として貸し出す、また家を建て替えてアパート経営をするなど、さまざまな選択肢があります。
リフォームや建て替えも早めの検討が必要
老後の住まいを考える際、住み替えだけでなく、リフォームや建て替えの選択肢も忘れてはなりません。
それぞれの選択肢にはメリットとデメリットが存在しますが、ここで考慮すべきは主に自身の収入源と住宅ローンの年齢制限です。
例えば、多くの金融機関では住宅ローンの年齢制限は70歳、返済は80歳までとなっています。
そのため、リフォームや建て替えを行う場合には、この条件を考慮に入れる必要があります。
また、新しい住まいを購入する際には、予算に合わせて中古住宅を探すなど、コスト削減のための工夫も必要となります。
新築を避けて中古住宅を探すこと、退職後は通勤の必要がないので、予算に応じて居住エリアを柔軟に変えられることなどが、大きなメリットとなります。
それらの選択肢を早い段階から考えることで、老後の生活をより安心して過ごすことができます。
老後の住み替えを成功させるためのポイント
老後の住み替えは、失敗のリスクも考慮した上で、慎重に実施する必要があります。
ここからは、老後の住み替えを成功させるために、知っておきたいポイントを紹介します。
持ち家の価値を早めに知る
住み替えを実施する際、大きなポイントになるのが、今の持ち家を売却していくらになるのかです。
住み替え資金は、持ち家の売却代金が大きな割合を占めます。
そのため、持ち家がいくらで売れるかによって、購入する新居のグレードも変わってきます。
持ち家の価値は購入から年月が経つことで、経年劣化します。
また、周辺環境や物件の状況によっても増減することがあります。
現在の持ち家の価値は、不動産会社に査定を依頼することで、おおよその価値が分かります。
持ち主が抱いているイメージと大きく異なる可能性もあるため、早めに金額を知っておいた方が良いでしょう。
資金計画を早めに立てる
住み替えは、今の住まいの片づけや不用品処分、新居への引っ越し費用や新生活で必要な買い物など、何かとコストが発生します。
こうした状況を踏まえて、住み替え資金は早めに工面しておくことをおすすめします。
持ち家の売却で得られる代金は各不動産会社の査定額に基づきますが、必ずしも査定の通りの金額で売れる訳ではありません。
思ったような金額で売れなかった場合なども想定して、住み替え費用はある程度確保しておく必要があります。
安全性と利便性にも目を向ける
老後の住み替えは、デザイン性や立地以外に、安全性や利便性にも目を向ける必要があります。
住み替え後は、加齢によって屋内の移動や階段の昇り降りがどんどん難しくなっていきます。
住み替え後のことも考えて、バリアフリーに目を向けた住み替え先選びが重要になります。
資産価値も考慮する
子ども世帯へ相続することも検討している場合は、将来的に資産価値を維持できるかどうかも考慮する必要があります。
資産価値が将来上がる見込みのない持ち家を相続しても、簡単に売却をすることができません。
実際に住んでいなくても固定資産税は毎年かかるので、子ども世帯に負担を残すことになってしまいます。
円滑で意味のある相続を想定しているなら、将来的に資産価値を維持できるかどうかにも目を向ける必要があります。
老後の住み替えは失敗のリスクも考えよう
30~40代とは異なり、老後の住み替えは終の棲家をみつける作業となります。
理想を詰め込むだけでなく、老化により不自由が多くなることも想定をした上で、慎重に購入先を選んでいきましょう。


 当サイトは東晶貿易株式会社が
当サイトは東晶貿易株式会社が