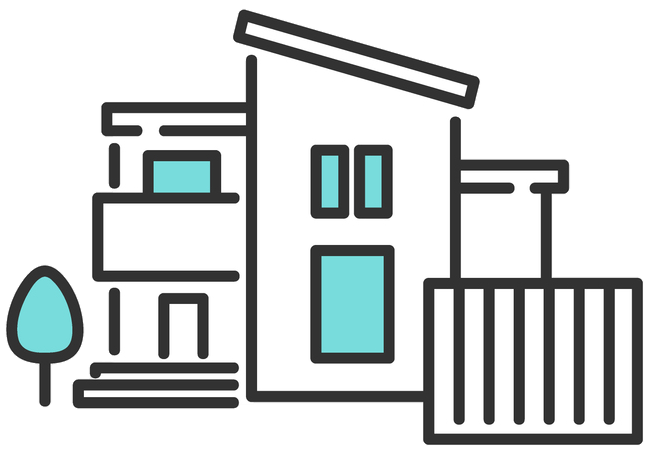不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
固定資産税は平均いくら払う?税率の仕組みと計算方法・シミュレーション・軽減措置(減税・減免)を解説
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
不動産を所有している限りついて回るのが、固定資産税の支払いです。
固定資産税は決まった金額が一律に課税される訳ではないので、課税の仕組みと計算方法を知っておく必要があります。
今回は固定資産税の平均から計算方法、減税制度などを紹介していきます。

固定資産税とは土地・家屋などに課される地方税のこと
固定資産税は地方税の一種で、不動産などのいわゆる固定資産に対して課されます。
基本的に固定資産税は不動産に例外なく課されるため、居住用だけでなく事業用不動産や農地なども課税対象になります。
固定資産税は土地・家屋1件(軒)ごとに課される
自宅に固定資産税の通知書が届いた場合、多くの方は「自宅に税金が課された」と認識にしています。
間違いではないですが、詳しく言うと住まいの建物部分と敷地部分それぞれに固定資産税が課されているので、実はまとめて2つの課税を支払っているのです。
固定資産税が課される不動産が1つか複数かというのは、意外に難しい問題です。
例えば、更地にラインを簡素に引いた駐車場は土地として見なされますが、屋根や大がかりな設備が建っている駐車場は土地+建物と見なされます。
納屋や物置、倉庫なども規模によって建物と見なすかどうか変わってくるので、事前に専門家へ確認を取ることをおすすめします。
固定資産税の平均額を戸建て・マンションの相場別に紹介
固定資産税の課税額は、どんなタイプの物件を所有しているかによって変わってきます。
例えば、戸建てかマンションかによっても平均額は変わるため、注意が必要です。
ここからは、戸建てとマンション、それぞれの課税額の相場を紹介していきます。
戸建ての固定資産税の平均額は10~12万円
戸建ての固定資産税は平均10~12万円ほどで、マンションや土地よりも高額になります。
戸建ての課税額が高額なのは、建物+敷地で2つの不動産の評価額が合わさるためです。
ただ、戸建て住宅は非常に個別性が高く、特に注文住宅は購入者の要望によってデザイン・設備がバラバラなので、課税額にも非常にズレが生じる点に注意しましょう。
マンションの固定資産税の平均額は8~10万円
マンションの固定資産税の平均額は8~10万円で、戸建てよりも低めです。
マンションの敷地は部屋の専有面積に応じて区分所有するのが一般的なため、価格が低くなるのです。
固定資産税評価額に占める土地評価額の割合が小さいのは課税者にメリットが大きくなります。

建物部分の固定資産税評価額は原則、築年数の経過に応じて減少していきます。
しかし、土地には経年による劣化の概念がないので、評価額は基本的に横ばいとなります。
築古になって価値がほぼ0になった戸建ては土地部分の評価額を元に課税されるので、戸建て(建物+敷地)に占める敷地部分の割合が大きいと経年で建物の評価額が安くなっても大した節税効果は見込めません。
一方でマンションの場合は建物部分が全体の固定資産税評価額に占める割合が大きいため、経年による節税効果が見込めます。
固定資産税を決定する固定資産税評価額の仕組みとは?
不動産の評価価値の中に、固定資産税評価額というものがあります。
その不動産の固定資産税を算出する際のベースになる金額のことで、以下の計算式で求められます。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%※標準税率
固定資産税は実勢価格(時価)とイコールではありませんが、基本的には実勢価格をベースにしているので、相場推移は比例してきます。
固定資産税評価額は実勢価格に比例して推移する
固定資産税評価額は実勢価格に比例して推移します。
つまり、固定資産税というものは毎年金額が変動するものなのです。
変動の要因は様々ありますが、物件自体の劣化の他、周辺環境や経済情勢の変化によっても課税額は変わるものです。
建物の固定資産税額は原則下がっていく
建物は築年数の経過によって価値が年々下がってきます。
そのため、固定資産税の課税額も年々下がるのが一般的です。
物件を所有していれば課税額は減っていきますが、一方で維持コストは増加していきますし、売却した時の手残りも減ってしまいます。
また、固定資産税の負担は必ずしも時間と共に減っていく訳ではありません。
例えば、東日本大震災(2011年)直後の不動産相場が下落したタイミングで購入した物件は、2013~2018年あたりに起こった東京オリンピック特需の真っただ中で価値が購入当時を上回ったケースもあります。
これは、物件の価値下落を上回る勢いで地価が高騰していたことが原因です。
このように、必ずしも固定資産税はセオリー通り推移する訳ではないので、注意が必要です。
固定資産税と共に支払う都市計画税とは?
固定資産税と共に、地域によっては都市計画税の支払いが義務化されている場合もあります。
都市計画税とは、都市計画法に基づき整備・開発・保全などの必要があると見なされた都市計画区域の中で、市街地を形成している区域や10年以内に市街化すべきと見なされている区域に課される税金です。
固定資産税評価額が課税の根拠となり、以下の計算式で求められます。
都市計画税=固定資産税×0・3%
つまり、都市計画税の対象となるエリアを保有している場合、最大で固定資産税評価額×1.7%を支払う必要があります。
固定資産税の課税額を決定する6つの要因
不動産に課される固定資産税はマンション・戸建てなどで一律に定められている訳ではありません。
主に以下6つの要素によって課税額は決定するため、課税額は不動産によってバラバラです。
- 築年数
- 構造
- 面積
- 立地
- 適用される税率
- 地価の推移
ここからはそれぞれの要素の内容を見てきましょう。
要因➀築年数
戸建て・マンションといった建物の固定資産税評価額は、築年数の経過によって下がります。
築年数の経過による価値の減少スピードは一般の方が思っている以上に早く、戸建ての場合は築20~25年ほどで、マンションの場合は築40~45年ほどでほぼ0になります。
ただ、土地には築年数という概念がないので、建物部分の価値が0になっても敷地部分に固定資産税は課され続けます。
要因②構造
前述のように戸建てのほうがマンションより早く0になるのは、マンションが主に鉄筋・鉄骨造なのに対し、戸建ては木造が多いためです。
このように、価値の下落スピードは建物の構造によって大きく変わってきます。
法定耐用年数では、構造別に安全に利用できる年数を以下の通り定めています。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 軽量鉄骨プレハブ造(厚さ3mm以下) | 19年 |
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨プレハブ造(厚さ3mm~4mm) | 27年 |
| 重量鉄骨造(厚さ4mm以上) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
要因③面積
同じ立地・築年数などの条件であれば面積が広い土地や建物ほど固定資産税評価額は高くなります。
これは面積が広ければ広いほど評価が高いと見なされているからですが、広すぎる不動産は価格の割に利用しにくいことが多いため実際の人気は低いケースも多々あります。
要因④立地
地価は都市部ほど高く、郊外・田舎になるほど低い傾向があります。
同じ面積・構造の戸建てでも首都圏をはじめとする都市部に建てるのと、郊外に建てるのでは、固定資産税が10倍近く変わる可能性もあります。
要因⑤適用される税率
固定資産税の税率は年1.4%となっていますが、全国一律ではなく、自治体によって1.4%以外の税率を採用しているところもあります。
税率によって納付額は大分変わるので、役所の窓口に確認しておきましょう。
固定資産税とあわせて支払うことの多い都市計画税も税率0.3%と良く言われていますが、これは最大の税率であり自治体によって細かい違いがあります。
要因⑥地価の推移
固定資産税評価額の根拠になる地価そのものが推移すれば、課税額も予想以上の変動を見せます。
地価が変動する要因は、以下が挙げられます。
| 要因 | 例 |
|---|---|
| 周辺環境の変化 | 新駅・道路の開通など |
| 経済情勢・金融情勢の変化 | 大地震や景気悪化、ローン金利の変動など |
| 需要の高騰・減少 | 不動産投資家の殺到、商業施設の開発、住宅街としての人気など |
地価は激しく頻繁に変動する性質ではありませんが、それでも上記のような理由で、一般の方が理解しているより簡単に変動するので注意が必要です。
固定資産税の計算方法を初心者にも分かりやすく解説
実際に固定資産税はいくらになるのか、計算する方法を分かりやすく紹介していきます。
ちなみにここからの解説は戸建ての計算方法を対象にしますが、その場合は建物と土地を別々に計算するようになります。
まずは家屋の計算方法から見ていきましょう。
建物の固定資産税の計算方法
建物部分の固定資産税は、以下の式で計算をします。
建物の評価額×1.4(固定資産税税率)
これだけ見ると単純ですが、肝心の建物の評価額の計算が非常に複雑なので注意が必要です。
建物(家屋)の評価額=評点1点分の価格×床面積×1㎡あたりの再建築費評点×経年原点補正率
上記の用語を解説すると、以下のようになります。
- 評点:不動産評価に関わる築年数、面積などの要素。項目ごとに点数が変わる。
- 再建築費評点:評価対象となった家屋と同一のものを、現時点・同じ場所に再建築した時に発生する費用を点数化したもの
- 経年原点補正率:過年数に応じた減価率
これらの項目を求めて正確に計算するのは初心者には難しいため、時価の7割ほどの概算で計算することが多いです。
土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税は、建物とは全く異なる計算で求めます。
土地の評価額(土地面積×路線価) ×1.4(固定資産税税率)
ここで重要になってくるのが路線価です。
土地が接している路線の価値のことで、国税庁が提供している路線価図から算出することができます。
建物より単純ですが、初心者は路線価図の読み取りに苦労することが多いので、以下の記事を参考にすることをおすすめします。
→路線価図の見方・計算方法固定資産税の減税・軽減措置を解説
固定資産税の税率は必ずしも1.4%で計算する訳ではありません。
固定資産税を節税できる、代表的な特例制度を3つ紹介します。
土地に対する固定資産税の特例
土地は以下の特例制度によって、固定資産税を削減できます。
- 小規模住宅用地の特例
- 一般住宅用地の特例
こちら2つの特例の内容をまとめたのがこちらです。
| 小規模住宅用地の特例 | 一般住宅用地の特例 | |
|---|---|---|
| 適用 | 土地の200㎡以下の部分 | 土地の200㎡超の部分 |
| 該当部分の評価額 | 6分の1 | 3分の1 |
例えば、条件を満たした400㎡の土地があれば、最初の200㎡は小規模住宅用地の特例が、残りの200㎡は一般住宅用地の特例が適用されます。
建物に対する固定資産税の特例(新築)
家屋に対する固定資産税の特例は、新築住宅にのみ適用されます。
内容としては、2020年3月31日までに新築された物件は、戸建てが最初の3年間、マンションが最初の5年間、評価額を2分の1で計算するというものです。
ただし、この特例が適用されるのは床面積120㎡以内の部分に限定されます。
例えば、床面積240㎡で評価額2,000万円のマンションにこの特例を適用すると、1㎡辺りの評価額×120㎡+(1㎡辺りの評価額×120㎡)÷2=1,500万円となります。
省エネリフォームに対する固定資産税の減額
省エネ改修工事をおこなった住宅は、翌年の固定資産税額(120㎡以内)が3分の1に減額されます。
この特例が適用されるのは2008年4月1日~2022年3月31日の期間で実施された改修工事が対象であり、減額される対象はリフォーム翌年分の固定資産税額に限ります。
固定資産税を納税する際のポイント・注意点
固定資産税の計算方法について理解したら、実際に納税をおこなう際はどうすれば良いのかについて学んでいきましょう。
納付は納税通知書に基づいておこなう
固定資産税は、不動産を所有する限り毎年支払います。
固定資産税の金額や納付の時期は毎年4~6月ごろに自宅へ届く納税通知書に記載されており、こちらに基づいておこなわれます。
金額は上記で説明した通りとは限らないので、必ず通知書の内容を確認しましょう。
現金振込・分割払いが一般的
固定資産税の支払いは、金融機関やコンビニATMから振り込むことで簡単に納付できます。
また、固定資産税は月4回分割で納付するのが一般的ですが、希望を言えば一括納付に変更も可能です。
評価額が想定より高い場合は審査の申し出ができる
通知書に記載されている固定資産税評価額が想定よりも高いと、それに応じて課税額も高くなります。
予想以上に評価額が高い場合、固定資産評価審査委員会というところに審査を申し込むことで、評価額が安くなるケースもあります。
評価額の根拠である基準地価は全ての土地についている訳ではないので、稀に実際より高額になっているケースも考えられます。
ただし、審査の要請は納税通知書の受け取りから60日以内までにしなければいけないので注意しましょう。
固定資産税の計算に関するポイントをおさらい
固定資産税はいくら課されるのか?
戸建ての固定資産税は平均で年10~12万円ほど課されます。
戸建ては建物と敷地に課税されるため、税額が高くなりがちです。
また、注文住宅の場合は課税額にばらつきが生じやすいです。
マンションの場合は、約8~10万円と、戸建てよりも低めです。
固定資産税はどう計算するか?
建物(戸建て・マンションなど)の場合は、建物の評価額×1.4(固定資産税税率)で計算をおこないます。
建物の評価額は、評点1点分の価格×床面積×1㎡あたりの再建築費評点×経年原点補正率で算出することが可能です。
土地の固定資産税は、土地の評価額(土地面積×路線価) ×1.4(固定資産税税率) で算出されます。
固定資産税は売却価格から算出するのが最も簡単で正確
国土交通省が提供している路線価図から公示地価を求めて税額を計算する方法も良くおすすめされていますが、初心者が簡単にできる方法ではなく、ミスが頻発しがちです。
それよりも不動産会社に面倒な計算をしてもらい、売却価格を出してもらってから税額を計算するのが最もスムーズです。
まずは、不動産会社に査定をお願いしてみましょう!


 当サイトは東晶貿易株式会社が
当サイトは東晶貿易株式会社が