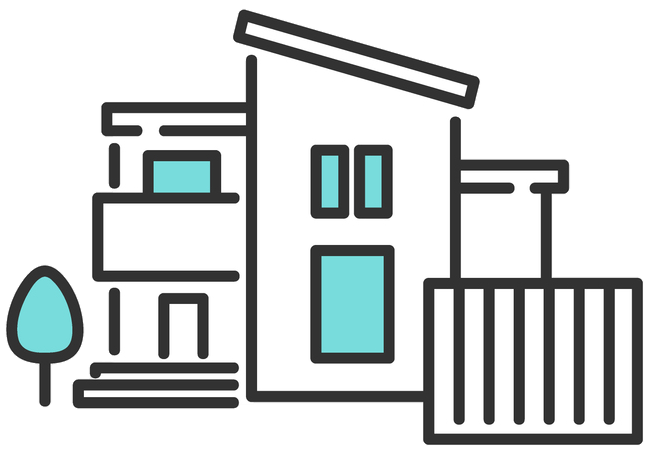建物オーナーにとって、消防設備点検は資産を守るためにも定期的に実施されなければいけないものですが、2018年の消防庁の調査によると報告率は「49.8%」。
なんと半数以上の方が報告をしていないことが分かっています。
なぜこのような事態になってしまっているのか、消防設備点検の現状・課題を詳しく解説していきます。
また記事の後半では、消防設備点検の未実施0をビジョンに掲げる株式会社スマテンのIT化による取組みについてインタビューしました!
火災による死者の約8割が住宅火災によって亡くなっています。
住宅火災で亡くなる方の多くが逃げ遅れによって火災に巻き込まれており、特に高齢者が逃げ遅れてしまう傾向にあります。
キッチンコンロなどで火を使う場面は、人が生活する以上ゼロにすることは出来ません。
重要なのは火災の発生をいかに迅速に住民へ知らせるかであり、古いマンションでも定期的な火災報知器の点検が重要になってきます。
消防庁が2018年に発表したデータによると、同年3月31日時点での消防設備点検の報告率は49.8%と、半数を下回っていることが分かります。
消防設備点検がされていないマンションはいわば、車検に出していない自動車のようなもの。
今後どんなトラブルが起こっても不思議ではありません。
| 年 |
全体報告率 |
1,000㎡未満報告率 |
1,000㎡以上報告率 |
| 1980 |
15.3% |
11.7% |
31.4% |
| 1990 |
36.6% |
31.3% |
57.6% |
| 2000 |
40.0% |
33,7% |
61.9% |
| 2010 |
40.8% |
34.4% |
61.7% |
| 2015 |
48.0% |
41.2% |
70.1% |
| 2016 |
48.2% |
41.5% |
69.7% |
| 2017 |
49.2% |
42.2% |
71.5% |
| 2018 |
40.0% |
33,7% |
61.9% |
引用:消防用設備等点検報告制度について - 総務省消防庁
40年前と比べると報告率は大幅にアップしていますが、小規模設備を中心に、まだまだ報告が不足している部分も多くあり、対応が急がれます。
消防設備点検は本来、物件を所有するオーナーなら全員やらなくてはいけないものです。
ただ現在は、設備点検が実施されていない物件というのが非常に多くなっています。
当然ながら設備点検されていない物件は100%の安全が保証されている訳ではなく、大変危険です。
なぜ、こんなことが起こっているのでしょうか。
現状の課題をまとめてみました。
「100%実施しないといけない」という社会の雰囲気が形成できていない
防災会社が設備点検に赴いても、「うちは大丈夫です…」と断られてしまったという報告は多数あります。
そもそも消防設備点検は住民の命を守るものであり、大切な資産を守るものですから、オーナーにとっては100%利益のあるものであるはずです。
それでも点検を断るオーナーが多いということは、その重要性が正しく認識されていないこと、セールスの一種だと誤認していることが考えられます。
1回はやったけど継続して実施できていない
消防設備点検を一度は実施したものの、2回目以降をやってはいないオーナーは多いです。
これも、消防設備点検は継続して実施しないといけないという認識の不足が影響しています。
消防設備点検は定期的に実施しなければ意味をなさないので、注意が必要です。
消防設備点検の作業の煩雑さ
消防設備業はこれまで非常にアナログで、点検報告書への多数押印や来署の対応などの煩雑な作業が多々ありました。
こうした作業の煩雑さも消防設備点検が拡大しない一因でしたが、現在はルール変更が進み、点検アプリや電子申請などが導入されてきています。
オーナーの経営力低下・初心者の参入
リーマンショックや長年の不況で、2000年代中ごろは財政難に陥り、消防設備点検を依頼できないケースが増えてきました。
2010年代中ごろから景気は回復してきたものの、リーマンショック時の衝撃が尾を引いて、コストをできるだけ割きたくないという考えのオーナーが増えています。
また、東京オリンピック特需で不動産投資ブームが起き、初心者のオーナーが多数出現しました。
消防設備点検の重要性を知らない初心者が増加したことも、設備点検実施の割合が減っている一因と考えられます。
「報告すれば良い」理論は設備点検作業の質を下げかねない
消防設備点検の会社はピンからキリまであり、目視で数秒確認しただけで点検シールを貼り付けるだけの業者もあると聞いたこともあります。
報告率の低下を懸念し、こうした半素人の点検業者の活用も促進してしまえば、物件のリスクはより分かりにくくなります。
ちゃんとした業者に消防設備点検を依頼すれば、それなりの時間・コストがかかるものです。
こうした背景を考えずに国や自治体・公共機関が検査数の向上だけを強調すると、質の低い点検が増えかねません。
点検の質を下げずにどう報告率を上げるかが、今後の課題になってくるでしょう。
お話を聞いた人
株式会社スマテンの戦略やビジネスサイド・プロダクト統括を担当。
業界最大手のリフォーム事業会社へ入社後、営業で全国上位成績を複数回獲得。支店長代理業務を3年間従事した後、IT業界へ転身。
組織マネジメント力や営業力、企画力を活かし複数のスタートアップで新規事業開発や事業構築を経
験。
昨年までIT不動産ベンチャーで60名規模䛾拠点長とし
て、チャット・BPO組織の再構築など、主にマネジメント経験8
年間の実績を積みスマテンへ。
スマテンは消防点検の業務効率化を実現できる業界初の消防点検プラットフォームです。
導入した建物オーナーや管理会社は、管理物件の消防点検の状況が一目で確認でき、作業の大幅な効率化が見込めます。
Web上で面倒な作業を完結できるほか、消防点検の見積もりも設備ごとに算出してくれるので、無駄なコストのカットが見込めます。
今回は、そんなスマテンの詳しい内容や導入事例、今後の見通しについて、株式会社スマテン取締役の藤野さんのお話を聞いてきました!
| 運営会社 |
株式会社スマテン |
| 設立 |
2018年4月 |
| 事業内容 |
スマテンの企画・運営・開発 |
| 住所 |
- 東京オフィス
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-17三浦ビル3F
- 名古屋オフィス
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-23 アーク白川公園ビル5F
|
| 電話番号 |
03-5309-2471 |
| FAX |
03-5309-2472 |
| メールアドレス |
info@sumaten.co |
| 公式サイト |
https://corp.sumaten.co/ |
スマテンのサービス内容・メリット
―まずはスマテンのサービス内容について、教えていただけますでしょうか。
スマテンは、消防設備点検をが必要な建物オーナーと消防設備点検資格者をつなぐプラットフォームです。
消防点検はこれまで、オーナーが管理会社へ依頼をし、そこから設備会社へ連絡をして、点検業者に依頼をするというかなり非効率な図式になっていました。
オーナーにとって専門的な内容で良くわからない上に手間がかかりますし、ペンや紙で全てこなすような、旧態依然とした実情がありました。
従来、オーナー側と管理会社側のどちらか一方に向けたEXCELの演算ソフトなどはあったのですが、両者に向けてサービスを提供する、両者をつなげるサービスというものはありませんでした。
スマテンの導入によって点検者側の効率化・時短を実現してコスト削減するとともに、お互いのメリットを提供することが可能です。
スマテンの導入事例
―スマテンはどんな会社に導入されていますか?
これまでは管理会社と個人管理オーナーの導入がほとんどだったのですが、現在話が増えているのが事業会社です。
ロードサイドに店舗を構える物販・飲食店やネットカフェなどの店舗は、事業会社が管理会社に色々な業務と一緒に一括発注していることが多いですが、その一元管理・コスト削減のためにスマテンの導入を検討しているケースが増えてきていますね。
―スマテンはありそうでなかったサービスだと思うのですが、どういった背景で開発に至ったのでしょうか?
もともとは名古屋で点検会社を経営していたのですが、その際に現場で感じた上記のような疑問点を、プロダクト化したという感じですね。
細かいところまで基準・ルールが行き届いていないような業界で効率が悪い上に、管理会社の方でも敢えてフタをすることで商品価値が分からなかった節もあり、透明化も進みませんでした。
スマテンを導入すれば管理会社もより効率よく収益化を図れますし「もっと現場の方に適正価格で点検させたい」という思いも、製品に込められています。
加えて、消防点検のやり方というのも業者によってピンキリで、ずさんな点検でも消防署に報告しているので、検査の実情が分からなくなっているリスクもあります。
スマテンの点検アプリを利用することで実際に点検をしたという証拠を残すことも出来るので、正確に実施状況を把握することが可能です。
―最後にスマテンのサービスと会社全体の今後の見通しをお聞かせください。
我々は「消防設備点検の未実施率0の世界」をするためにあらゆる分野でのゼロの世界の実現を目指しており、例えば消防設備点検以外にも、以下のような点検作業への拡大を目指しています。
(2020年4月現在、すでに拡大している領域も含む)
- 貯水槽点検
- キュービクル点検
- エレベーター点検
- 防火設備点検
- 防火対象物点検
- 特定建築物調査
現在はむしろ領域拡大や新リリースに向けて、提携を募っている段階だと言えますね。
まずはそちらの提携を進めていった上で、オーナー・管理会社・点検者にとってより良いものを提供するのが第一に考えていることですね。
もっと大きな今後の展開で言うと、スマテンの普及が今後進んでいくと、建物の安全性に関するビッグデータが集積していきます。
全国の建物の安全性がスコアリングできるようになれば、ポータルサイトと提携をすることで、より正確な情報を消費者にも届けることも出来ます。
まだ具体的なプランは考えておりませんが、かなり多方面に進出できる可能性はあると思っています。
そのためにも上記と並行して、認知度向上もやっていかなければいけないと考えています。
<インタビューは以上となります。>
 不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】



 当サイトは東晶貿易株式会社が
当サイトは東晶貿易株式会社が