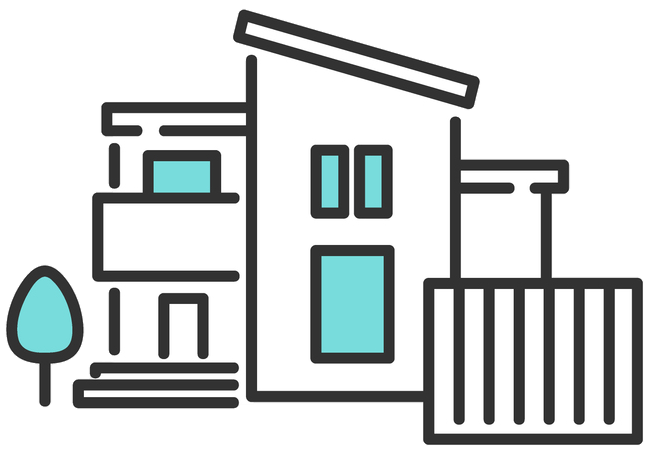不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
耐荷重って何?計算方法とオーバー時の注意点・家具やDIYでの使われ方を解説
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
「家の中の荷物が多すぎて、これ以上収まりきらない」「収納もできるおしゃれなインテリアを設置したい」
そのような時に設置するのが、フックやラックなのでの収納ですよね。
しかし収納とはいっても収納しすぎてしまうと、床や壁の破損につながったり、ケガの原因になったりすることも…。
収納家具を置く際には、必ず耐荷重(たいかじゅう)について考えなければなりません。
この記事では耐荷重やその他の表記について解説するとともに、フックやラックなどの収納家具を設置する際の問題点についてまとめています。
こちらを参考に耐荷重について理解し、適した収納家具を購入してみてはいかがでしょうか?
2023年最新インテリアトレンドのスタイルを予測!注目すべきカラー・テイスト・素材やアイテムは…?
耐荷重=ものが耐えられる重さ
収納家具などに表記されている耐荷重(たいかじゅう)とは何のことかご存じでしょうか?
耐荷重とはその記載されているもの自体が何キロまでの重さであれば、耐えることができるのかを示しています。
例えば、耐荷重が75キロの収納の場合、75キロまでの荷物であれば載せることが可能です。
このように耐荷重はそのものに何キロまでのものを置くことができるのかがわかる指標となっており、収納家具のスペックを測る際などには必ず見ておかなければならないポイントとなっています。
機能性が高いおすすめの室内物干し6選!選び方のポイントを徹底解説日本製の家具などに必ず記載されている
日本製の家具などには耐荷重が必ず記載されていますが、この場合の耐荷重はある程度ゆとりをもって設定されています。
そのため耐荷重を1キロオーバーしたからといってその家具が破損してしまうということはおそらくありません。
しかし耐荷重以下でもそのものが破損してしまうケースというのも存在しています。
例えば、重さが一か所だけに集中してしまうケースなどは稀に破損してしまうことがあります。
このようなケースを避けるために、基本的に重さは一点に集中させずに分散させることが必要となります。
皆さんも今家にある収納家具を確認してみましょう。
耐荷重以外の様々な重さ表記
私たちが日常使っている家具の中には、耐荷重以外にも様々な表記がされている場合があります。
ここからは耐荷重以外の家具に記載されている表記について解説します。
中々日常生活のなかでは見る事がないかもしれませんが、耐荷重をしっかりと理解するためにも見ておきましょう。
安全荷重
安全荷重は意味合いといては耐荷重とほとんど同じです。
しかし稀に耐荷重よりもその重さを低く設定することがあります。
その理由としては、記載しているものの強度を保証するために耐荷重にゆとりを持たせているからです。
もし安全荷重と記載されている収納家具を持っている際や購入する際には、この説明を参考に収納してみてください。
静荷重
静荷重という言葉を知っていますでしょうか?
静荷重は重りとなっているものが、止まっている状態で考えた際の耐荷重です。
これが仮にずっと止まっている状態ではなく、頻繁に移動させるとなった場合はどうなるでしょうか?
頻繁に移動させる方がそのもの自体は破損しやすくなってしまいます。
そのため静荷重と記載されている家具は、その数値を下回るのが理想的です。
フックやラックを設置する際の問題点や解決策
フックやラックなどの収納家具を設置する際には、そのものの耐荷重だけでなくその他のことにも注意しておかなければなりません。
ここからは収納家具を設置する際の問題点やそれに対する解決方法について解説しま
これから収納家具を置こうと考えている人は、必ずチェックしておきましょう。
床の耐荷重がオーバーする
ものを収納する際、家具だけの耐荷重を考えていれば大丈夫なのでしょうか?
そのようなはずがなく、家の中の床でさえその耐荷重は法律によって決められているのです。
建築基準法では、家の設計の際に㎡あたり180キロの重さに耐えられるように定めています。
その逆を言うと、㎡あたり180キロ以上の重りを置くことは床を破損させてしまう可能性が発生することになります。
実際は床が破損するという可能性は少ないですが、床がゆがんだりきしみの原因になったりとできれば㎡あたり180キロ以上の重りを置くことは避けた方がいいです。
床の耐荷重を多くするための解決策
床の耐荷重を多くするためには、重さを分散させることや床の強度を向上させることが大切です。
重さが一点に集中することを防ぐことによって、耐荷重を上回ることがなくなります。
もし自分の家で家具が一か所に集中しているようなところがある場合は、確認してみましょう。
また床の強度を向上させることは、床の厚みを増したり床の下に組まれている木材の本数を多くしたりすることによって可能です。
床の耐荷重に関して不安な人は以上を参考に実践してみてください。
壁の耐荷重がオーバーする
床と同じく壁にも平均的な耐荷重が存在します。
一般的に壁の耐荷重は壁一枚あたりにつき10キロまでです。
もし仮に耐荷重以上の重りを壁に設置してしまった場合、壁がゆがんだり破損したりする原因となってしまいます。
そのため耐荷重以上の重りを無理にかけることはおすすめできません。
壁の耐荷重を多くするための解決策
解決策としては壁にアンカーを埋め込むことや複数の壁によってフックなどの収納を支えることが挙げられます。
壁にアンカーを埋めることによって、一般的な耐荷重よりも少し多くすることが可能です。
しかし比較的大きめな穴が開いてしまいますので、賃貸住宅に住んでいる人は避けた方がいいかもしれません、部屋の隅などでは複数枚の壁を使うことによって、耐荷重を多くすることができます。
収納自体も安定しやすくなるので、筆者としても非常におすすめの方法です。
棚板の耐荷重がオーバーする
ラックのような複数の棚板で仕切られている収納家具があります。
このような家具は、それぞれの棚板ごとに耐荷重が設定されていることがほとんどです。
一般的には棚板は、天板や床に面している板などと比べると耐荷重が少なく設定されています。
そのため棚板に重いものを置いてしまって、棚板が破損したというケースも非常に多いです。
棚板の耐荷重問題を解決する方法
上でも説明したように、棚板は比較的耐荷重が少なく設定されています。
そこで解決策としては、棚板には重いものを置かずに天板や一番下段に重いものことが挙げられます。
天板や一番下段はラックの中でも耐荷重が多い方なので、重いものでも破損しにくいです。
意外にも棚板に重いものを置いているケースがあるので、皆さんも確認してみてください。
衝撃荷重という考え方
建築の際には衝撃荷重というもの関しても考える必要があります。
一般的には収納家具の耐荷重について考える際に衝撃荷重というものに関してはあまり考えないのですが、今回はこれについても解説してみましょう。
衝撃荷重とは、そのものがどれだけの衝撃に耐えることができるのかを示した言葉です。
地震大国日本では、衝撃荷重についてはしっかりと考えておかなければなりません。
例えば、地震が起きた際、50キロの重りを載せた収納はどれだけの衝撃が伝わるのでしょう?
50キロの重りが地震の影響で何倍もの衝撃をもたらします。
そのような際に、耐荷重を上回っていると家具の破損やケガの原因になってしまうことも少なくありません。
そのため衝撃荷重に関してもしっかりと意識しながら収納家具の設置をするべきです。
家を売る時に家具・荷物は片付けるべき?不要品のお得な処分方法を解説木材の耐荷重・たわみを計算する方法
耐荷重はDIYが好きな方や、プロの建築業者にとっても重要な要素になります。
特に、木材にどれくらいの重量を加えるとたわみが生じるのか、気になる方も多いと思います。
木材の耐荷重を計算する式は、以下の通りです。
Y=(W×L³)÷(4×E×b×h³)
難しい式に見えますが、一つ一つの意味を考えるとそこまで難しくはありません。
- Y=木材がたわむ幅(cm)
- W=荷重の重さ(Kg)
- L=支点間(テーブルの脚と脚の間など)の距離(cm)
- E=ヤング率(素材ごとの強さ)
- b=木材の幅(cm)
- 木材の高さ(cm)
ヤング率は素材ごとに異なりますが、2×4材は多くの場合SPF素材が用いられ、この場合は75000kgf/cmとなります。
例えば、180cmの2×4材に20㎏のものを乗せた場合、以下のように計算できます。
Y=1,049,760,000÷634,472,100=約1.65cm
この場合は、約1.65cmのたわみが発生するという計算になります。
安全率を導入するケース
上記が荷重によって発生する重みの基本的な考え方ですが、木材は個体ごとにズレがあるので必ず計算通りになる訳ではありません。
特に重いものを載せる時は、計算以上に木材がたわんでしまい、危険な場合も想定できます。
そこで、より重いものを載せるような商品の場合は大事を取って、以下のように2をかけた上でYを割り出して計算をします。
Y=(2×W×L³)÷(4×E×b×h³)
この2を安全率といいます。場合によっては2以上の数字をかけて計算する場合もあります。
耐荷重に幅がある家具の見方
物干し竿・突っ張り棒などの耐荷重は、パッケージに50~30㎏などと幅を持たせて掲載されていることがあります。
耐荷重に幅があるものは、取付寸法も100~200cmのように幅がある場合がほとんどです。
上記の計算式を考えると、取付寸法が短いほど耐荷重は大きくなり、長いほど耐荷重が小さくなることがわかります。
そのため、寸法100~200cm、耐荷重50~30kgの突っ張り棒なら、100cmの場合に耐荷重50㎏、200cmの場合に耐荷重30kgとなります。
足が伸びて高くなるタイプのアイテムなら、高くなるほど耐荷重は小さくなります。
耐荷重を知るとお得に買い物が出来る
耐荷重の考え方を知っていればお得に買い物をすることが出来るようになります。
例えば、お店に以下の2つの突っ張り棒が陳列していたとします。
- 寸法100~200cm、耐荷重50~30kg
- 寸法100~200cm、耐荷重50kg
後者のほうが良い素材を使っているため、200cmでも耐荷重は50kgとなりますが、価格もその分高くなる傾向にあります。
前者の突っ張り棒を寸法100cmで利用すれば後者と同じ耐荷重で使用できるので、安い価格で遜色ない使い方が出来ます。
このように、耐荷重の考え方が理解できるとお得に買い物することが可能です。
耐荷重オーバーは非常に危険
これまで解説した中でもうすでにお分かりだと思いますが、耐荷重をオーバーすることは大変危険です。
また衝撃荷重の考え方では地震の際にはさらなる衝撃が加わるため、載せる荷物はなるべく軽くすることが望ましいと思われます。
しかし耐荷重はある程度ゆとりを持っているものなので、すぐに破損する心配はないでしょう。
収納家具を選ぶ際には、収納する重さが耐荷重オーバーにならないように適切な収納を購入するべきですね。
人気の家具出張買取おすすめランキング!業者の口コミ・評判からサービスの特徴まで徹底比較適切な耐荷重を判断して安全にラックやフックを設置しよう
耐荷重やその他の重さに関する表記に関しては理解できましたでしょうか?
普段あまり意識していなかったことだと思いますが、耐荷重をオーバーしていた際には非常に危険な事故を起こりかねません。
収納家具を購入する際には、必ず耐荷重に注意しましょう。
この記事を参考に適切な耐荷重のフックやラックなどの収納家具を購入してみてはいかがでしょうか?
家具の転倒防止で最も効果がある方法とは?防止器具の種類と効果を比較
関連する他の記事
この記事では、不動産営業マンが使うカラ電のテクニックを紹介しています。
カラ電とは、顧客…

 当サイトは東晶貿易株式会社が
当サイトは東晶貿易株式会社が